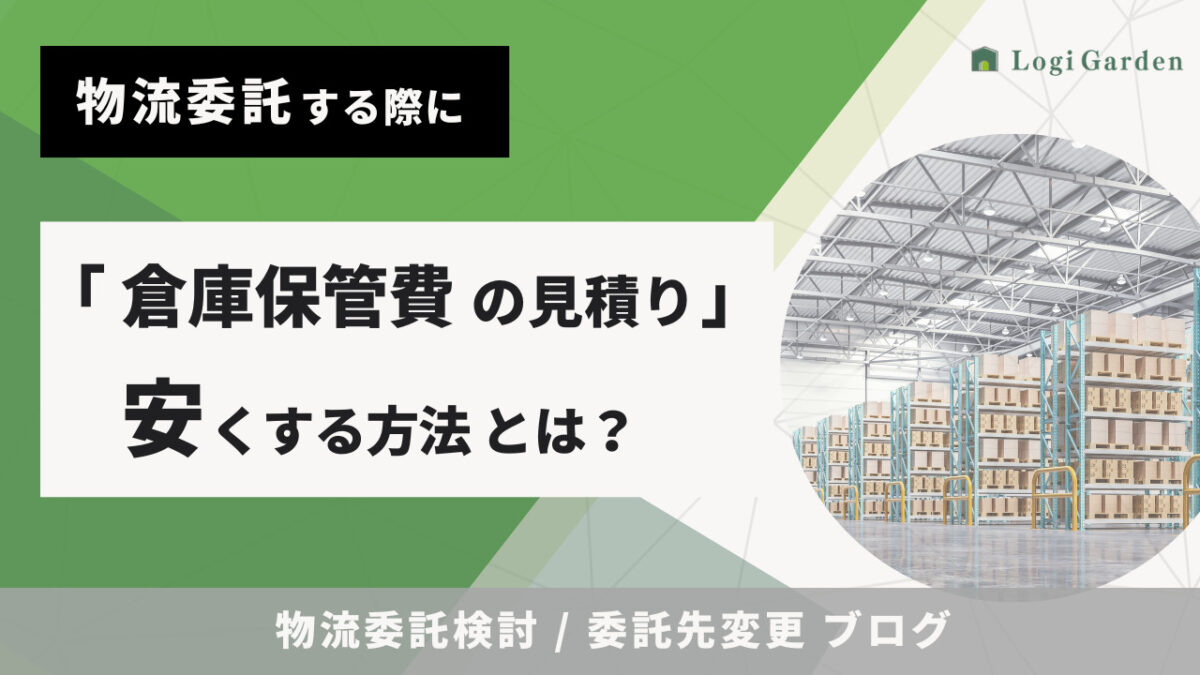倉庫保管費の見積り、もっと削減できるはず。でも、その方法は?
効果的な節約策を探求したくないですか?
物流委託の際の「倉庫保管費の見積りを適正にするためのポイント」を一緒に確認しませんか?
物流アウトソーシングには多くの利点がありますが、コストの透明性も求められます。物流委託時の倉庫保管費の適切な見積もり方を専門家の視点から解説します。あなたのビジネスの更なる成功のために、ぜひご一読ください。
はじめに
物流委託(物流アウトソーシング)を検討されている企業様、委託先を変更したいと計画している企業様にとって、倉庫保管費の見積りを安く抑えることはとても重要なことかと思います。
自社で物流を運営している場合は、倉庫を直接所有、もしくは直接賃貸する必要があります。今現在、日本の不動産価格は高騰しており、物流不動産においても同様です。さらに倉庫を建てるための建設費用や建設人件費も高騰しており、総じて新築の物流不動産物件は価格が高い傾向となっています。
さらに、新築の物流不動産の立地は、より郊外化しており、労働力確保の障害となっています。
この二つの傾向「倉庫不動産高騰」「倉庫不動産の郊外化」は、今後もさらに悪化していくでしょう。
このような、倉庫不動産領域(倉庫保管費)についての現在の課題や未来の不安に対しても、物流委託(物流アウトソーシング)には大きなメリットがあります。
一方で、物流会社側も、倉庫保管費(その他経費)に対して、利益分を上乗せして見積りを提案しますので、コスト(見積り単価)には、注意が必要となります。
本記事では、物流委託(物流アウトソーシング)する際に、いかに「倉庫保管費の見積り」を安くするための方法と交渉術を解説させていただきます。
倉庫の機能、役割、条件とは?
まず、倉庫についての解説をさせていただきます。
倉庫には、与えられた役割があります。一般的な倉庫を例に、下記に整理しました。
「倉庫を保管する機能」は、商品や材料を適切に保管し、管理できることです。
外的侵入を防ぐセキュリティ
自然災害に対する備え(最も発生確率が高いのが集中豪雨時の浸水リスク)
害鳥、害虫の侵入防止(最も発生確率が高いのがフン害)
清潔さの維持、換気通気性の維持(最も発生確率が高いのが湿気によるカビ被害)
「倉庫に荷物を入出庫するための機能」は、スムーズな倉庫運営の基本となります。
高床式によるトラック荷台との平行作業
広いヤード、トラックバースの確保、コンテナの取扱い可
荷物搬送のエレベーター、昇降機
「よい作業環境の条件」は、倉庫内作業の効率化の鍵となります。
空調、断熱構造、電気設備、高床式
適量の照度
作業スタッフの休憩室、トイレ完備、荷物保管ロッカー
「法令順守」については、最低限のリスク回避となります。
代表的なものは、建築基準、消防法、安全衛生、労働基準の4つになります
上記以外でも、冷蔵冷凍倉庫、危険物取扱倉庫、高度医療機器取扱倉庫や、個人情報Pマーク
取得倉庫、文書保管倉庫など、特殊な使用方法に特化した倉庫には、それぞれ必要な機能があります。
物流委託(物流アウトソーシング)をした場合には、上記のような倉庫の機能の整備や、保守などの維持管理は、委託先の物流会社が行ってくれるため、クライアント様(物販企業)は上記業務から開放されます。
一方で、物流委託(物流アウトソーシング)先の物流会社を決定する際に、倉庫設備や各種条件の詳細までを詰めていくことはとても重要ですが、実態としてはなかなかそこまで注意深く検討されている企業様は少ないのが現状です。
<倉庫保管費の見積りを安くするために、必要な知識を知ろう>
倉庫保管費の見積りを安くするためには、交渉先の委託検討先の物流会社様と交渉ができる最低限の知識を知る必要があります。下記に必要な知識を明記していますが、全てではありません。あまり長文になりすぎないように、他の物流情報サイトには載っていない知識を意識的に説明させていただきました。ご参考ください。
必要な知識①自社には、どんな倉庫が適しているのか?を整理すること
倉庫には、色々な機能と設備が必要となります。
しかしながら、全ての倉庫に、望んでいる多くの機能が搭載されている訳ではありません。新築だから安心ということは決してありません。また逆に言うと外観から判断できることは限りなく少なく、なんとなく新しいからというイメージで、倉庫を契約するのは大きなリスクを伴います。
また、機能面で最も重要なことは、各クライアント様(物販企業)のビジネスモデル、物流モデルに対応している必要があるということです。
B2C(特にEC)は、倉庫から直接エンドユーザー様へ商品が発送されるため、エンドユーザー様ライクな倉庫である必要があります。
B2B倉庫は、いかに多くの商品を工夫して、保管効率を高めて、倉庫保管料の負担を少なくするのかが重要視されます。多くはフォーリフトを利用しての運用となり、上記B2C倉庫とは、あらゆる面で方向性が違ってきます。
代表的な倉庫の機能を学んで、「自社に必要な倉庫機能」を書きだして要件定義しておくことが重要となります。
必要な知識②どんな立地である必要があるのか?労働力確保?
まず、立地(ロケーション)はとても重要な要素となります。
設備などの倉庫内環境は、後で設備投資して、増強することはできますが、立地(ロケーション)については、のちに変えたいとなると、大規模な引っ越しとなります。後日倉庫の選択で後悔することの多くは、後に変えることのできない条件を軽視していた為に発生していまうことです。
では、代表的な立地戦略(ロケーション戦略)での大事なポイントをお教えします。
| 1、人材確保 | 近辺での倉庫作業スタッフやフォーリフト人材確保条件が優れてる(人材確保ができる) |
| 2、自社施設との距離 | クライアント様(物販企業)のオフィスや工場に近い |
| 3、災害リスク | 大規模災害リスクが低い地域(固い地盤、海岸・川から遠い等々) |
| 4、宅配サービス | 宅配サービス会社の大規模集荷センターに近い |
| 5、委託先物流ネットワーク | 委託先の物流会社内の他の倉庫に近い。 委託先物流ネットワークが人的資源、設備資源が活用しやすい |
もちろん、地域の倉庫坪代(賃料)相場も重要となりますが、それ以外の要素が上記となります。また上記以外の要素も多数ありますが、ご参考ください。
必要な知識③倉庫は共有倉庫か?増減できるのか?拡張性があるのか?
次に、委託検討先の物流会社様から倉庫についての紹介・説明があった時、特に気にしてほしいのが、使用する倉庫敷地全体の環境・状況についてです。具体的には、紹介された倉庫は、クライアント様(物販企業)1社が全ての敷地を利用するのか?それとも複数の他のクライアント様も含めて、共有する倉庫なのか?を知る必要があります。さらに、委託検討先の物流会社様が、その倉庫の中で、どの範囲まで利用している(賃貸)のか?を知る必要があります。
そして、最も重要なことは、クライアント様(物販企業)のビジネスの事業計画では、必要な倉庫坪数(面積)が増えていくのか?減っていくのか?そして、事業計画の精度・実現性は高いのか?どうかを十分熟慮しながら、増減できる倉庫(倉庫環境)を、委託先の物流会社様と深く話をし、合意を得ることが重要です。
また、特に「使用坪数の増減の可能性」は、物流委託(物流アウトソーシング)する上での大きなメリットとなります。
しかしながら、倉庫という物理的な広さの制約があるため、増減の最大値については、その倉庫で可能な範囲が決まってくると思われます。
必要な知識④倉庫保管料として、坪代以外に費用は発生するのか?
「倉庫保管料という費用項目」に、何が含まれて、またその他にどんな費用が発生するのか?を、事前に詳しく、委託検討先の物流会社様に提示してもらうことが重要です。
特に気を付けたいのが、下記の3点です。
| 1、光熱費 @月額実費 | 主に電気、ガス、水道代。使用坪数相当分を負担。 |
| 2、共益費 @月額固定費 | 空調設備使用料。共有の通路・搬送エリア。メザニン。 屋根下(トラックヤード)。保守点検料等々。 |
| 3、保管設備費@月額準変動費 | 保管エリアの軽量棚、中量棚。物流ラック(ネステナー)等 |
委託検討先の物流会社様のそれぞれで、名称や含まれる要素も変わってきますので、必ず確認しましょう。見積り時点では不明確(例:実費表記)でも、契約時や初回請求書発行時に発生して、驚いてしますケースも多くあります。
必要な知識⑤倉庫保管料の妥当性、相場観を知るための基礎知識
ここでは、倉庫保管料の価格の妥当性や根拠、そして相場観を知るための基礎知識を説明します。
まず、大きく4つの項目を参考に、各エリア(地域)毎に、倉庫保管料が決められることとなります。
「築年数」「立地エリア」「倉庫規模/倉庫施設規模:使用床坪数」「倉庫不動産の種類」
築年数
| 「築年数」の見方 | 新築、新築相応の相場(~築12年以内) →坪単価が非常に高い →設備が充実。立地は郊外の確率が高い。 |
| 現実的な中古相場(築12~25年) →坪単価は妥当 →建築基準は安心(東日本大震災後に竣工) →過剰な設備がなく、費用対効果が高い | |
| 利用価値のある築古相場(築25年~40年) →坪単価は良心的 →建築基準は大きな問題はない (新建築基準適用1981年以降竣工) →設備に不安。設備造作も検討。 →立地は、住宅密集地に近い確率が高い。 |
立地エリア
倉庫保管料の相場観を知るためには、県単位だけでは、実態はつかめないので、地域や市単位で調査の必要があります。
関東を例にすると、現実的には、東京・神奈川については、坪単価相場は非常に高く、除外対象となります。次に、労働力確保の観点から、対象エリアは、「千葉」「埼玉」「茨城の一部」となります。また、関東の場合は、環状線(通り)を基準してみるのも分かりやすくなります。例:16号線内外、圏央道内外
いずれにしても、前述の「立地戦略(ロケーション戦略)での大事なポイント」を参考に、費用対効果・お得な相場観を考慮して、実際の倉庫選定に生かしていくことが重要です。
倉庫規模
総じて現在では、倉庫全体での使用可能坪数が5000坪以上の「大規模な倉庫」は、ランプウェイ型、またはマルチテナント型となっており、共有部分の建築コストが高く、また豪華な休憩所もあり、坪単価は割高となっている。
倉庫機能や設備として、上記のような倉庫が必要であれば検討する上で問題ないが、過剰な設備となっていないか?を、慎重に見極める必要があります。
一方で、5000坪以下の「中小規模な倉庫」で、新築の倉庫は非常に少なくなってきています。
既築の倉庫で、1000坪~3000坪の倉庫は、築年数が古い場合も多いですが、住宅密集地や都心に近い場合もあります。
大規模な倉庫も、中小規模の倉庫も、メリットもデメリットがあります。
今回の記事テーマは、「倉庫保管費の見積り(倉庫コスト)を安くする方法」ということもあり、それぞれのメリット・デメリットを詳細に調査して、分析して、自社の物流サービスにあった、費用対効果の高い倉庫を選択することが、とても重要となります。
倉庫不動産物件の種類
一般的には、「日本型経営の倉庫不動産会社」と「外資型経営の倉庫不動産会社」があります。
その中で、昨今増えてきているのが、ファンド型倉庫不動産とリート型倉庫不動産となります。どちらも、投資目的のための物件となります。
この投資型倉庫不動産物件については、とても魅力的な設備や外観で、素晴らしい物件ではありますが、注意する点があります。
それは、目的である投資家の利益確保が最優先であるため、契約期間中であっても、時に借主(クライアント様や委託先の物流会社)にとって厳しい条件を付けられる場合がありますので、契約条項等については注意する必要があります。特に、契約期間満了後の借主継続権利については、投資型倉庫不動産よりも、日本型経営の物流不動産会社が所有する物流不動産の方が、便利を図ってもらえるケースが多いかと思われます。
*ファンド所有の物流不動産とは?
ファンドは、投資家から集めた資金を運用して不動産を購入・運営し、その収益を投資家に分配する投資組織です。ファンドは、不動産だけでなく、株式、債券、他の資産にも投資することができます。
*リート所有の物流不動産とは?
リート(Real Estate Investment Trust)は、不動産専門の投資信託で、投資家から集めた資金を使って不動産を購入・運営し、その収益を投資家に分配する仕組みです。
両者の主な違いは、ファンドは多様な資産に投資することができるのに対し、リートは不動産専門であること、そしてリートは証券取引所に上場され、株式として取引されることです。
<倉庫保管費の見積り(倉庫コスト)」を安くする具体的な交渉について>
物流コストの一部を占める倉庫保管費、このコストをうまく抑えることが、ビジネスの発展に直結します。委託先候補の物流会社との交渉時に、倉庫保管費を安くするための具体的な交渉ステップをご紹介します。ぜひ、この記事を活用して、より効率的な物流運営を目指しましょう!
交渉ステップ①クライアント様から、倉庫条件を伝える(オリエン)
クライアント様は、物流会社に対して、必要な倉庫条件を伝えます。
実際に倉庫での現場オペレーション業務を行うのは、委託先の物流会社となりますので、物流オペレーションを円滑に行うための必要情報を漏れなく、伝える必要があります。
ここで重要な点は、「現在の使用している坪数」と「同じ坪数で、委託する訳ではない」ということです。ここは各物流会社様の腕の見せ所となります。
使用する坪数の内訳としては、「保管場所」「作業場所」「通路」があり、それぞれの適正は物流会社様の運用の仕方によって、また保管設備や作業フローによって、使用坪数は大きく変わってきます。
では、ここで委託検討先の物流会社様へ伝えるべき情報は、下記となります。
| 〇現在の使用坪数 *参考まで | 保管エリア坪数(棚数、棚段数) |
| 作業エリア坪数(入荷作業、出荷作業) | |
| その他坪数(資材置き場、通路、エレベーター等) | |
| 〇商品情報 | 現在在庫の商品分類情報(サイズや重さなど) |
| 〇在庫数実績 | 過去の在庫数実績推移(過去1年分) |
| 〇入荷数実績 | 過去の入荷数(入荷形態別@過去1年分) *入荷形態:コンテナ、ケース、ロット、バラ |
| 〇出荷数実績 | 過去の出荷数(出荷件数、出荷個数@過去1年分) |
| 〇在庫数予測 | 未来の在庫数予測(未来1年分) |
| 〇入荷数実績 | 未来の入荷数予測(入荷形態別@未来1年分) |
| 〇出荷数実績 | 未来の出荷数予測(出荷件数、出荷個数@未来1年分) |
| 〇未来の商品計画 | 未来の取扱計画商品情報とサイズシェア(未来1年分) |
特に、使用する坪数を、委託先の物流会社に試算してもらうために、さらに必要な情報がないかを聞くことも必要となります。
交渉ステップ②物流会社から候補倉庫物件を提案してもらう(プレゼン)
物流会社は、クライアント様から伝えられた情報や条件に基づいて、候補となる倉庫物件を提案してくれます。提案される物件は、使用可能坪数、設備情報、図面、坪単価、契約年数、物流不動産種類を含む詳細な情報が明記されているかと思います。必要な情報がなければ、追加で要望してください。
下記は、一つの例となります。また評価する上での最低限必要情報でもあります。
・使用可能坪数:〇〇〇〇坪
・使用可能時期:〇〇年〇〇月から
・倉庫設備情報:高床式、空調環境、照度(LED)、高さ、使用可能電気容量、
荷物昇降設備(エレベーター等)、床荷重、休憩室等々
・倉庫図面 :倉庫全体図、使用可能地域図、電源配置図、トイレ配置図
・坪単価 :〇〇〇〇円
・倉庫契約年数:物流会社と倉庫不動産会社との契約期間
・倉庫物件種類:個人オーナー所有物件、企業所有物件、ファンド物件、リート物件
交渉ステップ③坪単価に含まれないコストを確認(念のため)
倉庫保管料(坪単価)には、倉庫にかかわる固定費用の多くが含まれているはずです。しかし、物流会社様によって、坪単価に含まれないコスト(例:光熱費、共益火、管理費、保管設備費、保険料等々)が、後日発生する場合があります。必ず、見積もり提示時点で、見積もりに含まれていない倉庫保管関連の請求項目がないかどうかを、念のために確認してください。
交渉ステップ④拡張性・可変性の確認
このステップはとても重要です。物流委託(物流アウトソーシング)の大きなメリットである倉庫坪数の可変について、好意的な回答を得る必要があります。また口答で不十分であり、見積り条件や契約条項に追加してももらう必要があります。
多くのクライアント様の場合、ビジネスの拡大や縮小に応じて、また季節商材によって、倉庫の使用坪数は増減する可能性がとても高いと言えます。
具体的な内容としては、坪数の増減希望の単位は?増減希望の事前告知タイミングは?など、多くの取り決めをする必要があり、そのプロセスの中で、別途伝える情報も増えてくるかと思われますが、手間を惜しまず、建設的に進めていきましょう。
交渉ステップ⑤請求坪数の計測基準と計測単位/日程を確認
倉庫保管料の請求金額は、「坪代単価×坪数」です。通常は、使用する坪数に応じて計算されます。しかしながら、毎月の坪数の計測は、委託する物流会社様によって、各種条件が違います。
そもそも、1年単位で固定の場合もありますし、月単位の計測で、月末一回の計測の場合もあります。さらに細かく10日単位の月3期制の場合もあります。
どの条件が適正なのか?はクライアント様(物販企業)と委託する物流会社間で定めることとなりますが、見積り時や契約時に双方の合意の上で、決めることがほとんどです。結果として、「坪数の計測基準」「計測期間」および「計測日程」を明確にしましょう。
また、年に何度かは、計測日に立ち会う事をお勧めします。
交渉ステップ⑥倉庫を共有する企業/団体の開示依頼
提案された倉庫が、他の企業(団体)と共有であった場合、その企業の詳細を知ることは重要です。委託する物流会社に、共有する企業や団体の情報を開示してもらい、倉庫見学を行い、共有する企業の物流運営状況を知る事も必要となります。
委託先の物流会社が、同じ倉庫の中で、他の企業の物流委託業務を担っている場合は、メリットもデメリットもあります。特にアパレルなどの季節によって繁忙閑散期が激しい場合は、人的リソースの確保が困難な期間があるかもしれません。一般的には、繁忙閑散期が重なっている組み合わせは、あまり望ましくはありません。逆に、繁忙閑散期の組み合わせが良い場合は、スムーズな人的リソース管理がしやすいという状況もあります。
まずは、同一倉庫の同一委託先の動向には、興味を持つことをお勧めします。
交渉ステップ⑦近隣の倉庫スタッフ採用実績の開示依頼
こちらも、非常に重要なポイントとなります。
昨今、物流関連の人材採用については、非常に厳しい状況にあります。また近い将来は、間違いなく状況が悪化する可能性が高いと思われます。特に確保がむずかしいのが、倉庫内軽作業スタッフおよびフォーリフト作業者です。どちらも、近隣から通勤してくれる場合が多いので、近隣の倉庫関連の求人状況、採用状況の把握は不可欠となります。
現在でも倉庫の立地を選択する上で、「近隣の人材採用状況」の優先順位は非常に高く、今後は最優先となる可能性が高いと思われます。
具体的には、オリコミチラシやタウンワークなどの紙媒体や、WEB媒体を確認し、同様の募集要項を探し、「時給」と「採用条件」を確認しましょう。また時間的に猶予があれば、数週間~2か月程度情報を集め、特に過去の募集が連続してどれくらい掲載されているか?(採用難易度を知るため)を調査する必要があります。
交渉ステップ⑧物流センター候補の提案依頼について
①~⑦までは、各種交渉する為の事前調査および情報収集のステップでしたが、ここからは具体的な交渉となります。まず初めに大事なことは、「はっきりと意思表示をする」ことです。
もし、提案された物件が条件に合わない場合は、他の物件を調整してもらいましょう。
また、同時期に、複数の物流委託検討先からも、物件についても提案してもらいましょう。
その際に重要なことは、「総倉庫保管費と坪単価の目安(希望)」を伝えましょう。
具体的には、「現在の倉庫保管料と比べて〇〇%削減」など、明確な数字を伝える事が重要です。
交渉ステップ⑨坪単価と総倉庫保管費の交渉について
さて、複数の委託検討先の物流会社様から、複数の倉庫候補が提案されることが大事です。
その中で、最適な各種条件を確認しながら、各物件を対比させる「条件&コスト対比表」を作成しましょう。この対比表は、社内の責任者や決裁者が資料を見ただけで、それぞれのメリット・デメリットが分かりやすくなるように、作成しましょう。
この対比表を元に、社内の情報共有と、各委託検討先の物流会社様との交渉をスタートしましょう。
さらに、「倉庫保管費の見積り(倉庫コスト)」を安くする方法で、最も重要なことが二つあります。
①「坪単価」だけに固執せず、「総倉庫保管費@月の絶対金額」を最優先することです。
その理由は、倉庫保管費は「坪代単価×坪数」であり、同じ物量でも物流会社様の「保管効率度合い」「業務フロー設計次第」で、坪数も可変するということです。ということは、坪数についての交渉も行うということとなります。
②倉庫関連の他の経費がないか?確認して、あれば倉庫保管料と一緒に交渉することです。
例えば、空調環境が必須である場合、その光熱費が坪代単価に含まれるのか?を再度確認し、総トータルでの単価を交渉します。
結果として、この記事で最も重要なことは、「倉庫保管料の仕組みを知ること」と「坪単価だけでなく坪数を交渉」により、総倉庫保管費を安くすることとなります。
「倉庫保管料の見積り」を安くする方法 まとめ
アフターコロナ時代のビジネス環境は、大きな変化の渦(うず)の中にいます。物流の世界も、驚くほどの変化と革新が求められています。今まで多くの物販企業様が躊躇してきた物流委託(物流アウトソーシング)をチャレンジする企業も増えてきています。
物流の改善、および物流コストの削減は、過去も今も、大きな可能性を秘めています。その中で、倉庫保管料の適正な見積りは、その一歩として、専門家の素晴らしい知見を存分に活用することで、驚きの効果を実感できます。そして、コストの見直しも大切ですが、それ以上に大切なのは、物流戦略思考です。そして、委託先の物流会社との信頼関係を深めることで、より良い、明るく安定した未来が広がります。
この記事を読んで、物流の最適化のための新しいアイディアやインスピレーションを得られたら、幸いです。最後に、ビジネスの成功は小さな一歩から。物流のプロに相談することで、新しい扉が開かれるかもしれません。前向きに、そして賢く取り組みましょう。
私達、LogiGaden(ロジガーデン)では、
物流ノウハウや情報を発信する「物流ブログ」と、
良心価格で長く続けられる「物流コンサルティングサービス」を提供しています。
二つの取組みで、物流に携わる皆様のご支援ができるように努めてまいります!ので、
何卒ご愛顧のほど、よろしくお願いします。