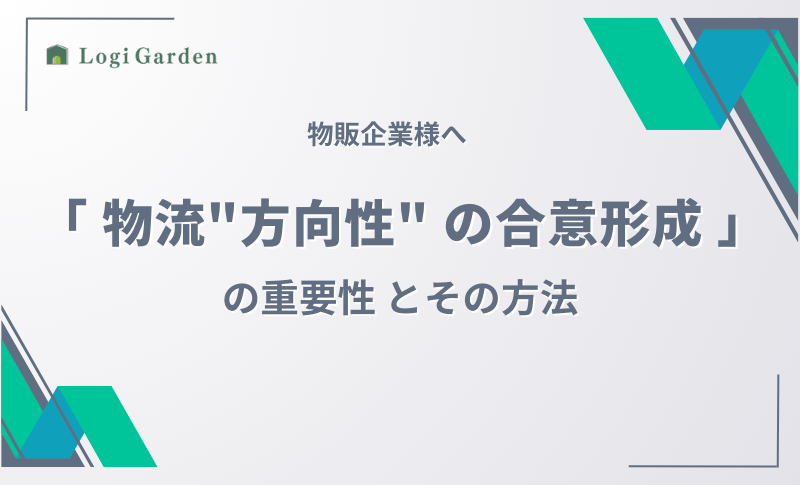はじめに
この記事では、「物販企業様で、自社で物流運用している皆様」と「物販企業様で、物流委託している皆様」に役立つ「社内の”物流の方向性の合意形成”の重要性とその方法」について解説していきます。

物販企業様で、自社で物流運用している皆様、物流委託している皆様の共通点は、”事業の主な目的は、商品やサービスの提供” であることです。同じ物流業務を担っている3PL物流会社様との大きな違いは、ここにあります。
物販会社様の物流部門で、物流に携わる多くの皆様にとって、今回の記事はとても意味あるものです。
社内の ” 物流の方向性の合意形成 ”の重要性について
前述しましたが、物販企業様にとっての主目的は、”事業の主な目的は、商品やサービスの提供”であり、
物流は目的を遂行するための手段となります。ここが最も重要なポイントです。
その為、物販企業様の経営層や各部門責任者様が考える物流の役割は、各個人毎に変わってきます。
それは知識と経験の差だけではなく、置かれているポジション、役割が違うためです。
具体的な例としては、あくまでも一般論ですが、
販売部門責任者は、物流部門が大きな滞りなく出荷・入荷業務をこなしてほしいと思いがちです。
経理財務部門責任者は、物流部門はコストセンターであり、コスト削減を最優先と考えがちです。
経営企画責任者は、物流こそ大事なマーケティング機能の一つであり、差別化を望んでいる傾向です。
人事責任者は、物流部門人材の教育は難しく、長く続けてほしいと考えがちです。
経営層は、一時的に上記のどれかに偏る傾向があり、経営環境の変化によって可変しがちです。
ここで質問です。
どの部門責任者の考えが、正解なのでしょうか?
答えは、どの部門責任者も正解であり、不正解でもあります。
ここで伝えたいのは、各部門責任者様にとって、自らの役割を全うする為には、物流部門との連動が不可
欠であり、物流部門に対する何かしらの思い(=要望、方向性)を持っているという事です。
この事自体は、決して悪いことではありません。物流部門はそれ程、事業推進する上で重要なハブ(車輪の中心部)の存在であると言うことです。
さて、ここまで長く、「社内の ” 物流の方向性の合意形成 ”の重要性について」話してきましたが、伝わりましたでしょうか? 伝わったとしたら、とても嬉しい限りです。次に具体的な進め方、より良い方法を説明したいと思います。
社内の ” 物流の方向性の合意形成 ”の方法について
それでは、重要性をご理解いただいた後は、” 物流の方向性の合意形成 ”の方法について解説します。
経営層や各部門責任者と合意形成をとる
主に、3つのポイントがあります。
そして、合意形成をとっていく順番があります。
合理的かつ有意義に、他部門との合意形成をとっていく為には、下記の3つの順番にそって、合意形成
をとっていく事をお勧めします。
●順番①
「今現在の自社の物流はコストセンターになってしまっているのか?サービスセンターを目指すべきなのか?」=コスト削減が最重要かサービス強化が最重要なのか?を決める。
●順番②
「今現在、売上・顧客の満足度を大きく下げている物流課題はあるか?」=物流部門に対する評価を聞き、課題があれば最優先で取り組む。
●順番③
「未来の社会課題、そして今後の自社物流サービスに求める事はあるか?」=1年後3年後に分けて、各部門の理想の物流の姿を聞き、物流部門の価値を高めていく。
なぜ、上記の順番なのか?が皆様、気になるかと思います。それは、経営層の考える順番であるからです。経営とは、経営資源を活用して、売上・利益を最大化していくのが目的であり、それは営利目的である会社組織の目的でもあります。
①利益の最大化 > ②顧客満足の最大化 > ③未来への投資
ここまで、話してきましたが、上記は多くの会社様の物流を担ってきた物流ベンチャーでの私の経験と知識から得たものであり、一般論の一つです。各企業様のビジネス状況や環境は、それぞれ大きく違います。事業ステージや競合環境も大きく影響してきますので、” 物流の方向性の合意形成 ”の回数を重ねていき、独自の優先順位を確立していくのが最良の道かと思います。
経営層や最終決済者様と最終確認する
前述で、経営層や各部門責任者様との合意形成をとっていく方法を伝えましたが、上記を行った上で、資料をまとめて、最終判断を経営層や最終決済者様に、改めて最終確認する事を強くお勧めします。
重要な事は、最終決済者(オーナー)、経営層(代表、取締役、事業責任者等々)の皆様が、現時点で物流をどう捉えているのか?今後どうしてきたいのか?の方向性を話し合う事がとても重要です。
そして、ここでの合意形成は、焦らず時間的余裕をもって、議論を重ねていく事をお勧めします。
(中途半端な合意形成の中で進めていくのは、大きなリスクが伴います)
何故なら、最終決済者、経営層にとって、物流は事業展開していく上での重要なインフラではあるが、一方でコスト・費用が発生するコストセンターでもあります。そして顧客満足を向上する重要なサービスでもあります。
これは、極端に白黒つけるのではなく、どちらを重要視するのか?どれくらい重要視するのか?という程度で結構です。ですが、物販企業様の中で物流に携わる多くのメンバーにとって、最終決済者、経営層(=会社)の物流の方向性を確認しつづけることは重要な行為の一つとなります。またこの方向性は、時に変わるものと捉えていくのが最善でしょう。
合意形成した事と合意形成できなかった事(それぞれの意見)を共有する
さて、多くの工数をかけて、” 物流の方向性の合意形成 ”をとっていく流れを解説させていだきましたが、もっとも大事な事は、共有することなります。共有する方法にも、大きなポイントが3つあります。
| 一つ目は、資料として可視化すること。 |
| 二つ目は、経営層・各部門責任者にプレゼンすること。(年度の定例会議の開催をお勧めします) その後、共有したデジタル資料を誰もが閲覧できる環境に置き、周知すること。 |
| 三つめは、合意形成した意見と合意形成できなかった意見のどちらも共有すること。 |
他部門ヒアリングは定期的に計画的に。
物流戦略共有は重要経営会議タイミングと合わせて、年2回から
一度、” 物流の方向性の合意形成 ”と共有を行った後は、運用していく事が必要です。ここで大事な事は、「物流の方向性は、臨機応変に変えるべきもの」ということです。
物流部門単独で、物流改善進捗状況や人的リソースの影響で、勝手に変える事ではなく、会社の業績や、販売戦略の転換、組織変更により、物流部門以外の方向性が変化していくのが常です。
販売と物流が連鎖していく事が、事業活動の原理原則です。
他部門の状況が変化していくことを事前に察知して、他部門との協調を事前に行い、物流部門も対応していくことが、重要です。
その為にも、お勧め手している事は、
” 物流の方向性の合意形成 ”の、他部門へのヒアリングは定期的に計画的に。
そして、物流戦略=物流の方向性の共有は、会社の重要な会議や経営タイミングに合わせて、年2回から始めてみることをお勧めします。
”物流の方向性の合意形成”の重要性と方法 まとめ
ここまで、物販企業様の「物流の方向性の合意形成 の重要性とその方法」について、説明させていただきましたが、ご興味をいただけましたでしょうか?
もっと詳しく知りたい方、さらに具体的な方法を知りたい方はいらっしゃいますでしょうか?
LogiGaden(ロジガーデン)では、物流改善の具体的な施策について、もっと深堀りして発信してきたいと計画しております。各種準備が整い次第、随時ブログにて発信させていただきます。
私達、LogiGaden(ロジガーデン)では、
物流ノウハウや情報を発信する「物流ブログ」と、
良心価格で長く続けられる「物流コンサルティングサービス」を提供しています。
二つの取組みで、物流に携わる皆様のご支援ができるように努めてまいります!ので、
何卒ご愛顧のほど、よろしくお願いします。